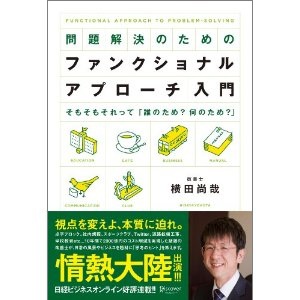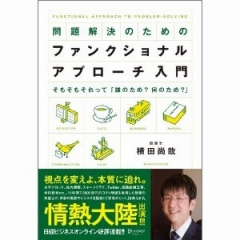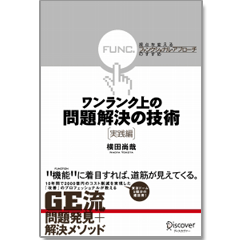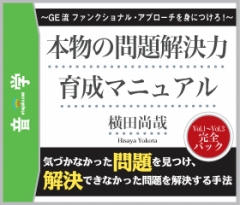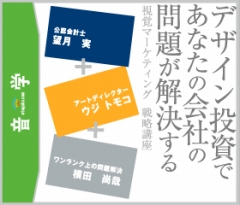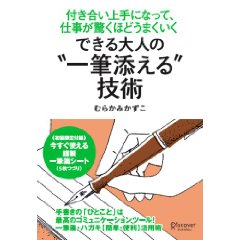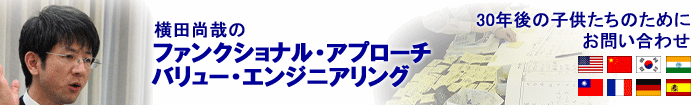 |
|||||||||
FA研究所
個別面談

皆さまからの声

毎月映像配信

DVD多数販売

会員制度

賛同者募集中

公式ブログ
ついったー
フェイスブック
視点を変える!
オトガク出版
これだけ注目
感激!大盛会
購入者特典
適正な小遣い?
携帯サイト
当サイト内のいかなるコンテンツも無断転用を禁止します。
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Copyright(c) 2007-2025 kamuna. All Rights Reserved.