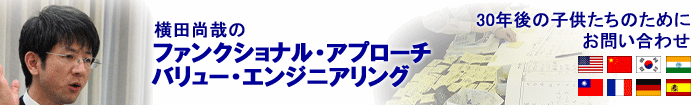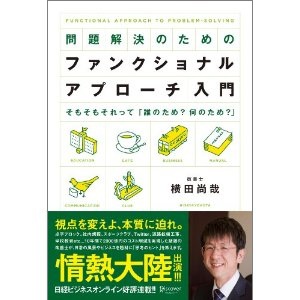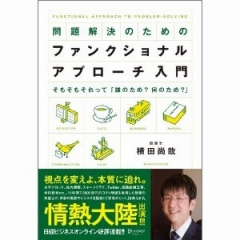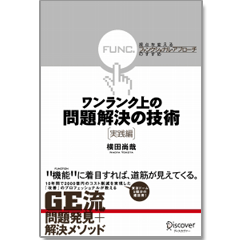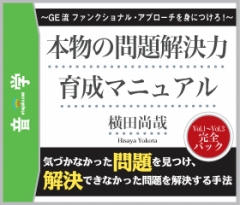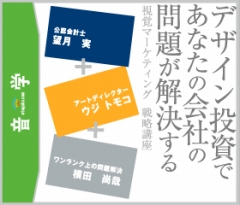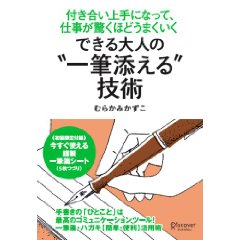出張のときに乗った地下鉄の天井で発見しました。ん〜、普通と違う。普通は、水平にパイプがあり、そこからつり革がぶら下がっています。でも、このつり革は、天井から直接ぶら下がっていて、水平のパイプはありません。 天井から直接ぶら下がっているとはいえ、天井板の裏には、強度に耐える部材(専門用語でバックアップ材と言う)があるはずです。その部材は、どうやら空調機器を支える部材と兼用しているようです。 そもそもは、つり革の機能は何でしょうか。《体重を支える》機能や《位置を固定する》機能があるのでしょう。 じゃ、よくある水平のパイプは、どんな機能があるのでしょうか。このパイプは、直接つかむこともできるものもあります。ということは、《体重を支える》機能があるのでしょう。しかし、直接つかめないパイプもあります。やはり、《つり革をつなげる》機能しかないのでしょうか。それであれば、写真のようなつけ方の方が、無駄がないですよね。 とかんがえていたら、電車が急ブレーキ!ゆれる体をつり革で支えようとしたのですが、つり革が長いため、体が大きく動いてしまいました。なるほど! 水平パイプの機能には、《つり革の長さを短くする》機能があるのですね。そしてそれは、《つり革の動きを少なくする》機能の達成に役立っているのでしょう。これで、納得です。 満員電車では、こんな機能も最近出てきました。《手の位置を示す》機能です。手を下げていると痴漢と間違えられるため、両手でつり革を持っておきます。「バンザイ通勤」というものですね。
|